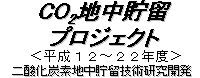|
|
 |
全国貯留層賦存量調査
 目的 目的
わが国の帯水層においてCO2を貯留できるポテンシャルのあることを十分な信頼性をもって示すことにより、その有効性を評価することを目的として、以下の項目を実施しました。
|
|
| 新たな地質情報・知見に基づくCO2地中貯留可能量評価 |
|
|
|
| 排出源近傍におけるCO2地中貯留の可能性評価と貯留量の算出とその精度向上 |
|
 CO2地中貯留のカテゴリー分類 CO2地中貯留のカテゴリー分類
地質調査結果ならびにCO2貯留に関する新たな技術的観点を踏まえ、地中貯留量の算出を行いました。帯水層への貯留を、カテゴリーA「背斜構造への貯留」、カテゴリーB「層位トラップなどを有する地質構造への貯留」に分類しました。各カテゴリーは国による基礎調査(基礎試錐および基礎物理探査)等で取得された地質データの質・量によって評価精度が異なることを考慮し、さらにカテゴリーAを3つの準カテゴリー(A1、A2、A3)に、カテゴリーBを2つの準カテゴリー(B1、B2)に細分化しました。
地下深部塩水層へのCO2貯留のカテゴリー分類
| 地質データ |
カテゴリーA
(背斜構造への貯留) |
カテゴリーB
(層位トラップなどを有する地質構造への貯留) |
| 既存油ガス田 |
坑井・震探データ豊富 |
A1 |
B1
(水溶性ガス田) |
基礎
試錐 |
坑井・震探データあり |
A2 |
基礎
物探 |
震探データあり、坑井なし |
A3 |
B2(16海域) |
| 主なトラップメカニズム |
|
|
| Structural & stratigraphic trapping (構造および層位トラップ) |
|
|
|
| Solubility trapping (溶解トラップ) |
|
|
|
| Residual gas trapping (残留ガストラップ) |
|
|
|
| Mineral trapping (鉱物トラップ) |
|
|
貯留概念図の例
(カテゴリー分類) |
 |
 |
 貯留可能量の算出 貯留可能量の算出
岩野原での実証試験や他の実際の帯水層貯留の知見を踏まえ、以下の式で貯留可能量を算出しました。
| CO2貯留可能量 = Sf×A×h×φ×Sg/BgCO2×ρ |
| Sf :貯留率 |
φ :孔隙率 |
| (カテゴリーAは50%、Bは25%) |
Sg :超臨界CO2飽和率(50%) |
| A :面積(m2) |
BgCO2 :CO2容積係数(0.003) |
| h :有効層厚[層厚×砂泥比(m)] |
ρ : CO2密度(0.001976トン/m3) |
ここで、貯留率Sf (Storage Factor)は、帯水層の総孔隙体積に対する超臨界CO2を貯留する容積比率を示します。本調査ではCO2の浮力による鉛直方向の移動を考慮してカテゴリーAでは50%、カテゴリーAに比べ面積が広大なカテゴリーBは、水平方向の貯留層の不均一性も加味して25%を採用しました。
超臨界CO2飽和率Sgは、岩野原実証試験サイトの物理検層によるCO2飽和率検討値が40〜50%、ドイツの事例40〜60% (May et al.2004)、カナダでのシミュレーション結果30〜90% (Keith et al.2004)であることから、50%を採用しました。
上記のCO2貯留可能量の算出式を用いて、わが国のCO2概算貯留可能量を概算しました。その結果、カテゴリーAで301億トン、カテゴリーBで1,160億トンとなり、総計では1,461億トンの地中貯留が可能であると算出されました。平成5年度の概算結果(914億トン)に比べ貯留量が大きく増大している理由は、平成5年度以降の地質調査データが追加されたこと、及び平成5年度に仮定したCO2が水へ溶解して貯留されるという想定を見直し、超臨界CO2で貯留される割合が高いとしたこと等によります。
CO2地中貯留可能量算出結果
| 平成17年度 |
平成5年度 |
カテゴリー
区分 |
貯留可能量
(百万トン) |
カテゴリー
区分 |
貯留可能量
(百万トン) |
| A1 |
3,492 |
1 |
1,987 |
| A2 |
5,202 |
2 |
1,541 |
| A3 |
21,393 |
4 |
72,042 |
| B2 |
88,477 |
| B1 |
27,532 |
3 |
15,847 |
| 合計 |
146,096 |
合計 |
91,417 |
| ※内陸盆地、内湾(瀬戸内海、大阪湾、伊勢湾など)は対象外 |
| ※深度800m以深、かつ4000m以浅を対象 |
 排出源近傍におけるCO2地中貯留の可能性評価 排出源近傍におけるCO2地中貯留の可能性評価
地中貯留の有効性評価においては、貯留可能量に加えて排出源と貯留サイトとのマッチングが重要です。これは、地中貯留のコスト分析において、輸送に係るコストが相対的に大きな割合を占めることが明らかになってきたことによるものです。排出源近傍において地中貯留のポテンシャルを示すことができれば、今後の地中貯留の実適用が大きく前進することが期待されます。
既存資料をもとに我が国における貯留層調査の状況と各カテゴリー分類の位置を見ると、大規模排出源近傍である東京湾、大阪湾、伊勢湾、北部九州地域では地下深部のデータは少ないことがわかります。今後これらの地点で貯留の可能性を評価するためには、反射法による地震探査やボーリングなどの実調査が必要であると考えられます。
そこで、大規模排出源近傍の東京湾、伊勢湾、大阪湾、北部九州において、地質資料の収集整理、地質構造の検討、貯留対象層・遮蔽対象層の検討・抽出を踏まえて、CO2貯留可能量を一次試算しました。この試算により、大規模排出源近傍域の沿岸域で地中貯留の可能性があることを初めて明らかにしました。
 成果 成果
|
|
| 帯水層への貯留を、カテゴリーA「背斜構造への貯留」、カテゴリーB「層位トラップなどを有する地質構造への貯留」に分類し、さらにカテゴリーAを3つの準カテゴリーに、カテゴリーBを2つの準カテゴリーに細分化しました。 |
|
|
|
| 我が国のCO2概算貯留可能量を算出した結果、カテゴリーAで301億トン、カテゴリーBでは1,160億トン、総計1,461億トンであると算出されました。 |
|
|
|
| 大規模排出源近傍域の沿岸域で地中貯留の可能性があることが明らかになりました。 |
|
 今後の課題 今後の課題
|
|
| 既往資料や震探層序解析、ボーリング等による大規模排出源近傍沿岸域における貯留可能量の精度を向上させます。 |
|
|
 |